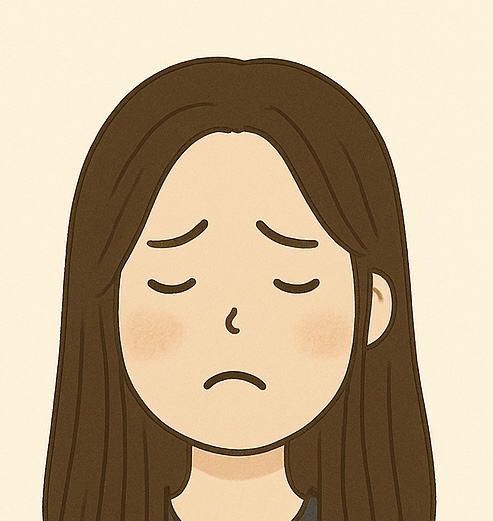 お悩みAさん
お悩みAさん宅食サービスで『冷凍』と『冷蔵』があるけどどっちを選べばいいのかわからない。
今回はそんな悩みを抱えている人のための記事です。
宅食サービスの選択次第で
✔︎ 夕飯の準備のラクさ
✔︎ 冷蔵庫・冷凍庫の使い勝手
✔︎ 無駄なく使えるかどうか
が、変わってきます。
特に「冷凍タイプ」と「冷蔵タイプ」は、それぞれ適した暮らし・使い方が異なるので、間違ったタイプを選ぶと“便利どころか逆にストレス”になることもあります。
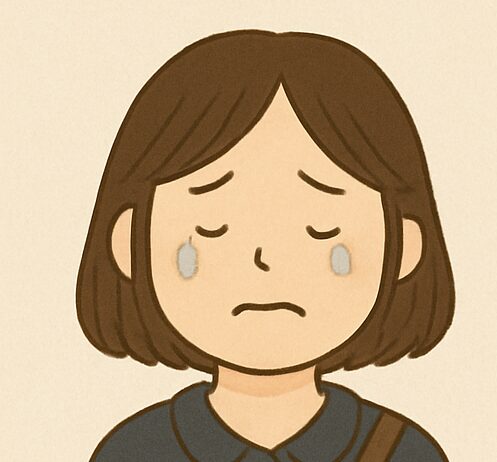
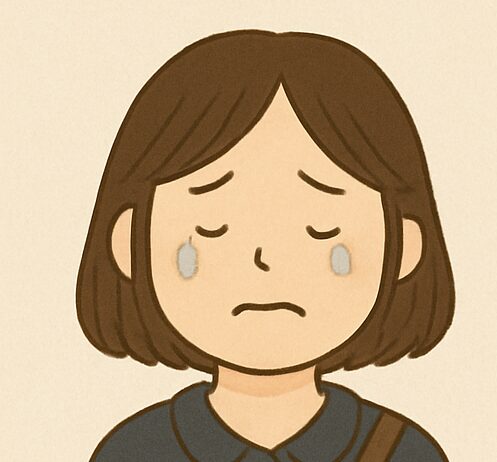
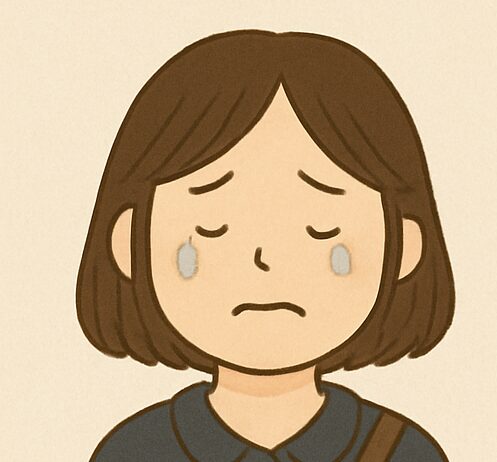
せっかくお金を払ってサービスを受けるんだから絶対に失敗したくないよね。
この記事では、宅食で冷凍と冷蔵のどちらが自分にとって本当に使いやすいかを、メリット・デメリット・実例を交えて明確に比較します。



この記事を読めばライフスタイルにぴったり合うタイプを選べて失敗しにくい宅食利用ができるようになるよ。
• 冷凍宅食と冷蔵宅食、それぞれのメリットとデメリット
• 冷凍 vs 冷蔵で「使いやすさ」がどう違うか(保存・賞味期限・受け取り・調理時間など)
• 自分の生活スタイル(帰宅時間・冷凍庫容量・献立の余裕など)に合うタイプの見極め方
• 冷凍・冷蔵タイプでおすすめの宅食サービス例
結論:共働き・帰宅が不規則・家事を減らしたい家庭には「冷凍宅食」がおすすめ
✔︎ 保存できる
✔︎ 受け取りやすくコスパが良い
✔︎ 予定変更に強い
これらの観点から生活リズムがバラバラになる可能性がある家は冷凍宅食がおすすめです。
ただし、味・食感・その日の鮮度を最も重視する家庭や冷凍庫が極端に小さい家は「冷蔵」が向きます
最終的には両者を“ハイブリッドで試す”のが失敗しない方法です。
理由:なぜ冷凍/冷蔵宅食で「使いやすさ」が変わるのか4つ観点で考える


ここでは「使いやすさ」にダイレクトに影響する4つの観点を丁寧に説明します。
1)保存期間と“予定変更”への強さ
冷凍は保存可能期間が長く(製品によるが数週間〜数ヶ月が多い)、冷蔵は鮮度重視で短期消費前提(数日以内)で作られています。
残業・外食・子どもの体調不良などで「当日食べられない」ことが頻発すると、冷蔵は廃棄が増える可能性があります。



冷凍なら食べられるタイミングでストックから取り出せばいいから廃棄リスクは少ないね。
「不規則に夕食がずれる頻度」が高いなら冷凍を選ぶ方が良いかもしれません。一方で毎日ほぼ同じ時間に家族全員が揃うなら冷蔵でもなんの問題もありません。
2)受け取り(配送)・在宅のしやすさ
冷凍はまとめ配送(週1回など)で受け取り回数が少ないことが多いです。
冷蔵は“日配”や“週何回かに分ける”スタイルがあるため在宅や受け取りの制約が出やすくなります。
✔︎ 受け取りに失敗してその日の分が痛むかも
✔︎ 再配達手続きが面倒
✔︎ 置き配の時間が長くて品質が心配
など、気になる人も多いと思います。
在宅が少ない、受け取り時間がバラバラなら「まとめ配送可能な冷凍」が負担を減らしてくれます。配達日に必ず在宅できる人は冷蔵でもOKです。
3)調理・温めの手間と“失敗リスク”
冷凍は解凍や温め時間が必要(電子レンジや湯せん)です。
冷蔵はそのまま盛り付け・短時間加熱で食べられる場合が多いです。
電子レンジの出力や加熱時間を間違えると仕上がりが悪くなる(熱ムラ、容器の溶損など)可能性があります。
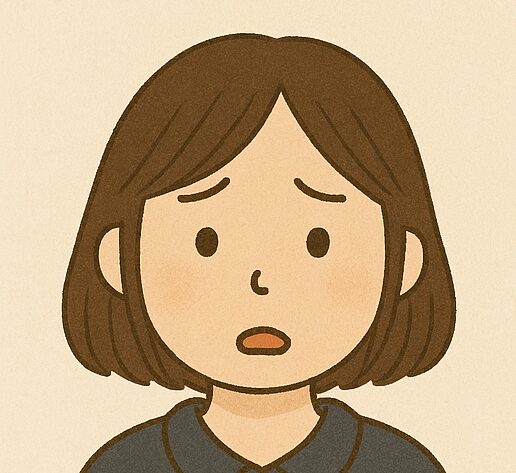
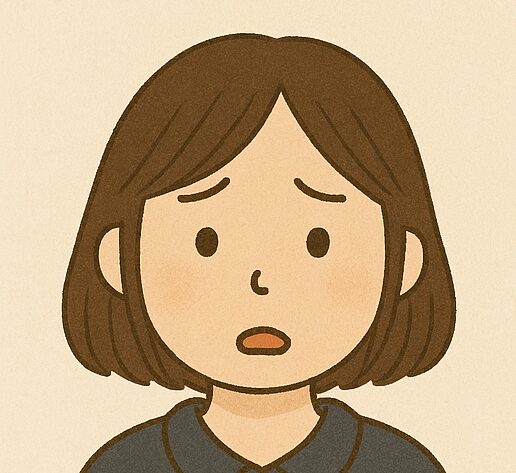
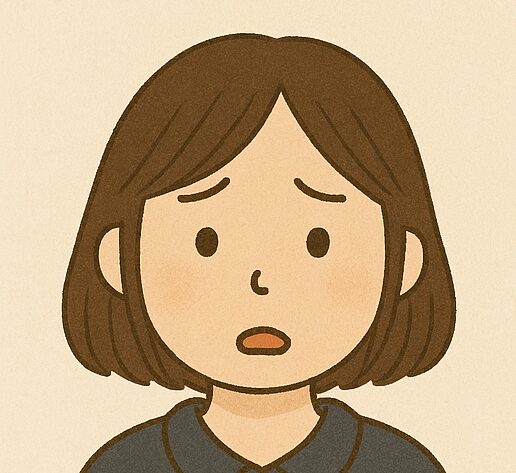
高齢者やお子様など、電子レンジ操作が苦手な家族がいると悩みになりますよね。
家族に電子レンジ操作が頼めない・火の扱いに不安があるなら、冷蔵や“加熱が確実に短いメニュー”の選択を検討してください。
4)設備(冷凍庫容量・設置環境)
冷凍はストック力がある反面、冷凍庫の物理スペースが必要です。
冷蔵は短期保管で済むため冷凍室の負担が少ないのが特徴です。
冷凍庫が小さいと
✔︎ 注文数に制限が出る
✔︎ 別の冷凍食品を置けない
✔︎ 買い物頻度が増えるなど不便が出る
と、せっかくの宅食サービスをストレスに感じるケースになってしまいます。
冷凍庫の実寸を測って“何食分入るか”をチェック(後述の「冷凍庫で何食入るかの簡単計算」を参照)してみて、明らかに入らない場合は冷蔵中心の宅食サービスを利用してみてください。
冷凍/冷蔵宅食のメリット/デメリット(詳しく・悩み解決的に解説)


ここではメリット・デメリットがどんな家庭のどんな悩みを解消/発生させるかをセットで紹介します。
冷凍宅食のメリット(+実際どんな効果を感じられるのか紹介)
- 予定変更に強い(保存性)
→ 残業や外出が多い家庭で「買って無駄にする」リスクを大幅に減らせる。 - 受け取り回数が少なくて済む(まとめ買い)
→ 週1回受け取ればOK。再配達の手間や在宅の縛りを軽減。 - コスパ面で有利(まとめ割・配送料節約)
→ まとめ買い割引や配送料の分散で1食あたりが安くなる傾向にあるので家計にやさしい。 - メニューの幅が広い(冷凍技術で保存できる品が増えた)
→ 季節メニューや複雑料理も冷凍で届くことが多く、バリエーション豊富。
冷凍宅食のデメリット(+困る状況と回避策を紹介)
- 冷凍庫を占有する(量的問題)
→ 小さい冷凍室の家庭は“注文数を減らす”か“冷蔵と併用”で対応。 - 加熱の手間・失敗リスク
→ 電子レンジ加熱の説明をキッチンに貼る、ラベルに「温め時間/ラップの剥がし方」を明記しておく。 - 食感の違い(揚げ物のサクサク感など)
→ 揚げ物はトースターで再加熱して復活させるなどの工夫でカバー可能。



より美味しく食べられるような工夫を試すのは楽しそうだね。
冷蔵宅食のメリット(+どういう悩みを解決してくれるのか)
- 作り立てに近い鮮度と食感
→ 味にこだわる家族、素材の食感を重視する場合の満足度が高い。 - 調理/仕上げの手間が短い
→ 高齢や子どものいる家庭などの電子レンジ操作が不安な家庭では手間・失敗が少ない。 - 冷凍庫スペースを圧迫しない
→ 冷凍庫が小さくても導入できる。毎日確実に消費できる家は合理的。
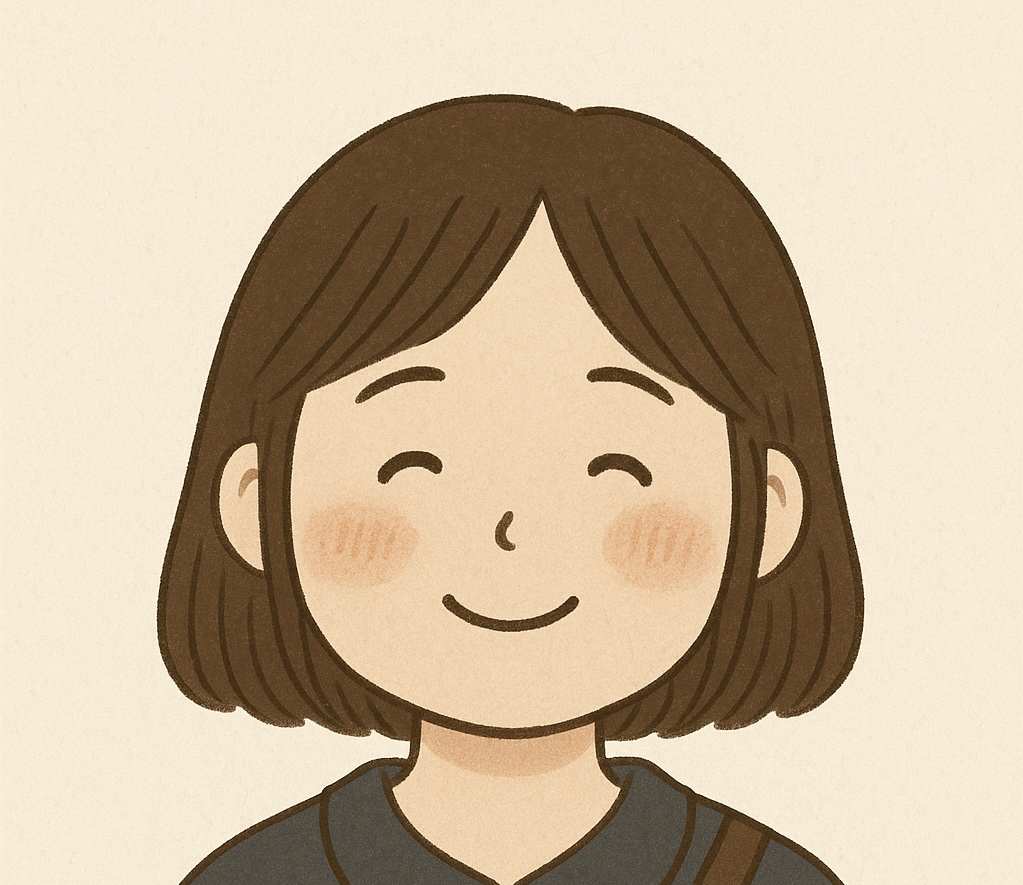
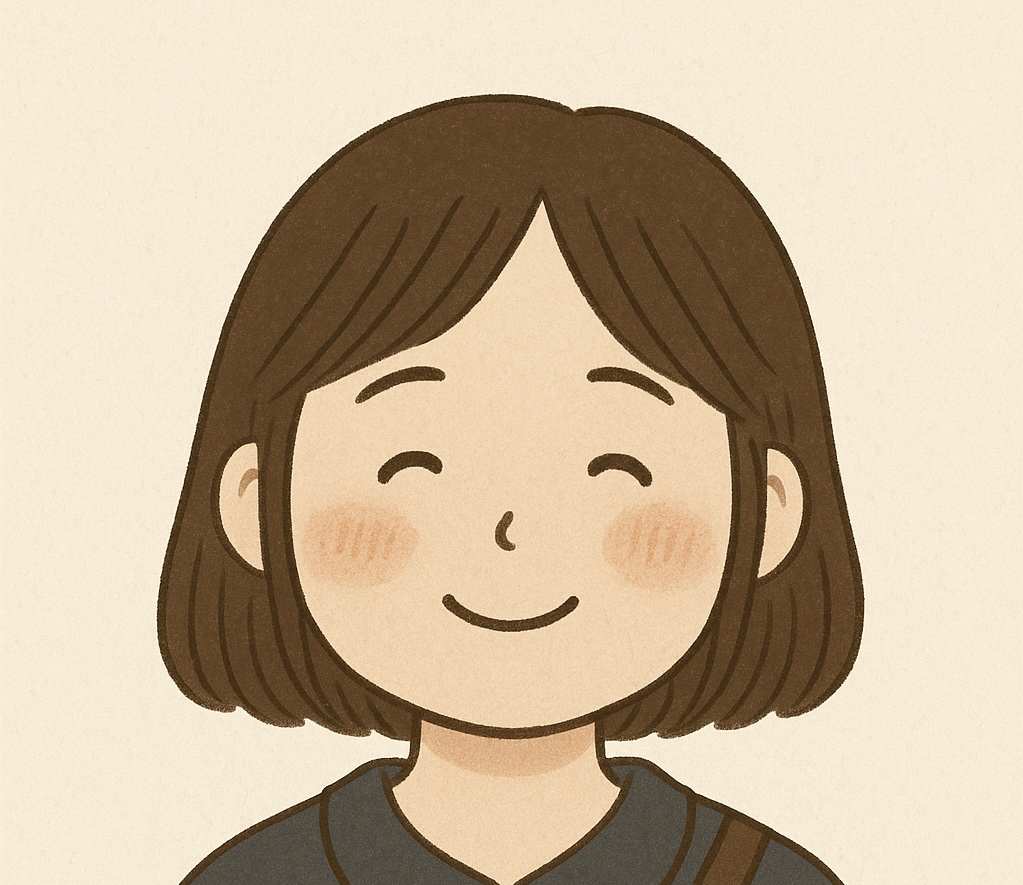
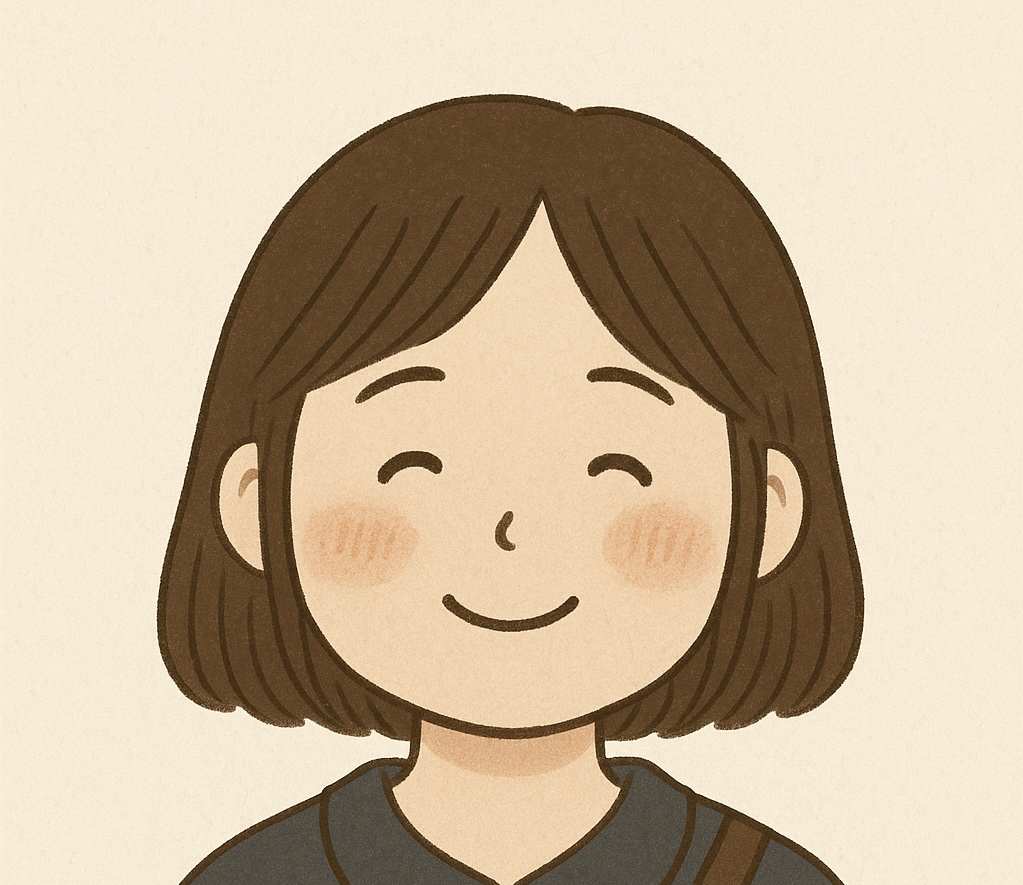
疲れている時や体調が悪い時にすぐに食べられるものがあるのって本当に助かるよね。
冷蔵宅食のデメリット(+困る状況と回避策を紹介)
- 賞味期限が短い(2〜3日)ための廃棄リスク
→ 受け取り日・食べる日を細かく決める「献立ルール」を作ると無駄を減らせる。 - 配送回数が増える→受け取り負担・送料増
→ 受け取りサービス(置き配ボックス)を契約するか、配達指定が柔軟なサービスを選ぶ。 - コスパが冷凍に劣るケースが多い
→ 価格比較・初回お試しを使ってコスト感を掴む。
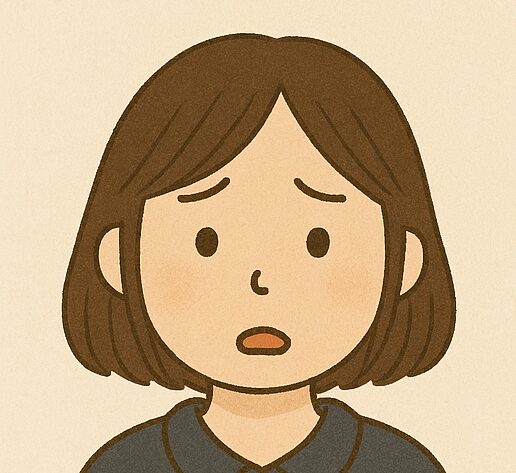
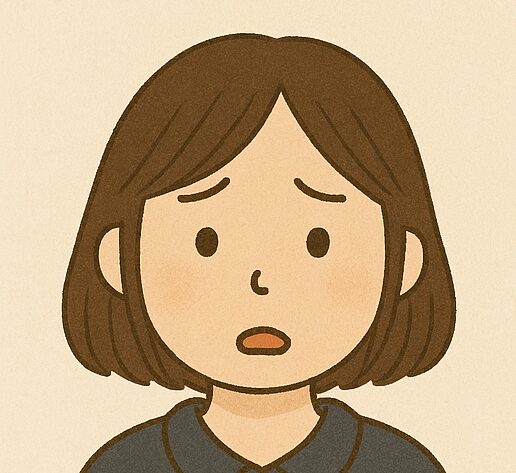
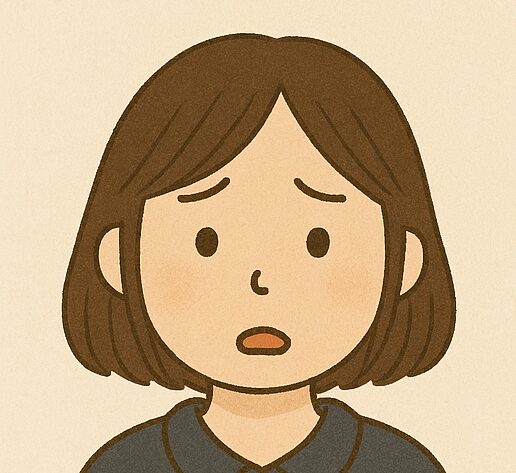
仮に1食あたり100円の差額だとしても1ヶ月頼んでいたら3,000円の差になるからバカにできないよ。
冷凍庫に何食入る?(簡単チェック)


冷凍宅食を本格導入する前に実寸で「自分の冷凍庫に何食入るか」を確認すると失敗が防げます。
その方法と例を紹介します。
実際に測るのが一番確実です。簡単チェック方法としてぜひ試してみてください。
計算方法(目安)
- 冷凍庫内の「横 × 奥行 × 高さ(cm)」を測る。
- 1食分のパッケージサイズ(横×奥行×厚さ)を測る。
- 各方向で「何個並ぶか」をそれぞれ小数点切り捨てで計算して掛け合わせる
と、収納可能数の目安が出ます。
具体例A(小さめの冷凍室)
- 冷凍庫内寸:横30cm × 奥行30cm × 高さ18cm
- 1食パッケージ想定:横20cm × 奥行14cm × 厚さ3.5cm
計算(端数は切り捨て): - 横に並べられる数 = floor(30 ÷ 20) = 1
- 奥行に並べられる数 = floor(30 ÷ 14) = 2
- 高さに積める数 = floor(18 ÷ 3.5) = 5
→ 収納目安 = 1 × 2 × 5 = 10食分
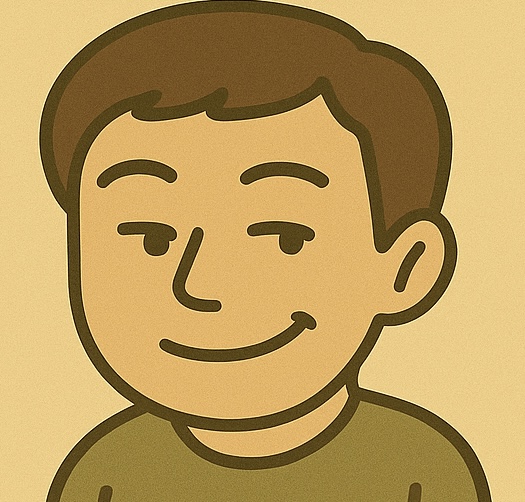
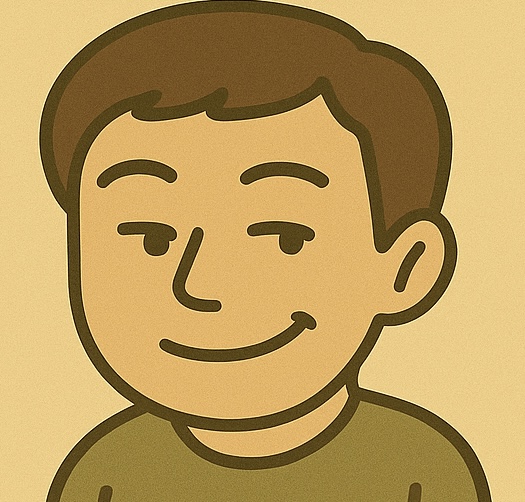
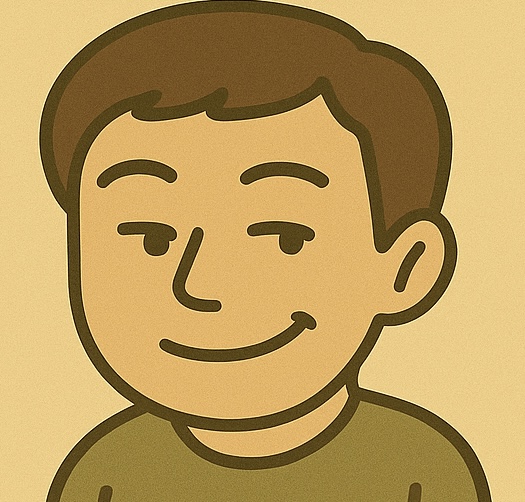
すごい簡単な計算方法だな。
具体例B(中くらいの冷凍室)
- 冷凍庫内寸:横45cm × 奥行35cm × 高さ25cm
- 同じパッケージサイズで計算すると:
横 = floor(45 ÷ 20) = 2
奥行 = floor(35 ÷ 14) = 2
高さ = floor(25 ÷ 3.5) = 7
→ 収納目安 = 2 × 2 × 7 = 28食分
※上の計算は目安です。実際にはパッケージ形状や冷凍庫の棚配置で多少変わります。
実寸を測ってから、何食頼みたいのか(週あたり)と照らし合わせましょう。
どんな家庭に冷凍/冷蔵宅食が合うのか?事例で紹介


ここではどんな家庭に冷凍/冷蔵の宅食が合うのか?事例と「おすすめの選択・実行プラン」を紹介します。
事例1:共働き(夫婦とも帰宅が遅い)/子ども小学生1人
- 悩み:帰宅時間がバラバラ。食事の準備に時間をかけられない。
- おすすめ:冷凍宅食をメイン。週1回まとめ配送でストック。
- 具体プラン:まずは「6〜12食のお試しパック」を注文して冷凍庫に余裕があれば次回から12〜20食パックに移行。
夕方は電子レンジで温めるだけ。揚げ物はトースターでリカバリ
夕飯準備時間が短縮され、外食が減り家計管理もしやすくなります。
事例2:高齢の両親と同居(電子レンジ操作に不安あり)
- 悩み:電子レンジの操作や塩分管理が心配。味の鮮度も重視。
- おすすめ:冷蔵宅食を試す(あるいは低調理で温めが短い冷凍)。配送日に合わせて盛り付ける運用。
具体プラン:冷蔵タイプを週に3日分だけ導入し、残りは自炊で補う。冷蔵の温め時間は2分以内のものを選ぶ。
味の満足度が高く、家族の食事の満足感を保ちやすいです。
事例3:冷凍庫が小さい一人暮らし(ワンルーム)
- 悩み:冷凍庫が小さく、ストックするとパンパンになる。
- おすすめ:冷蔵タイプを基本+冷凍少量(ハイブリッド)。
- 具体プラン:冷蔵の週2回利用をベースに、忙しい週だけ冷凍パック(3〜4食)を追加。冷凍容量は冷凍庫に入る個数で調整。
冷凍庫を圧迫せずに宅食の便利さを享受できます。
事例4:食費を抑えたいが時短もしたい家庭
- 悩み:家計重視で食費を抑えたいが、手間は減らしたい。
- おすすめ:冷凍宅食(まとめ買い)。ただし、1食あたりの価格・送料を合算して比較する。
- 具体プラン:1食あたりの価格が最安のプランを比較表で確認(例:1食¥500のプランなら月20食で¥10,000、送料¥1,000なら合計¥11,000)。
初回割引やクーポンでさらに下げる。
外食を減らしつつ時間も節約。コスパ改善が見込めます。
どう決めればいいかの実務フローで考える
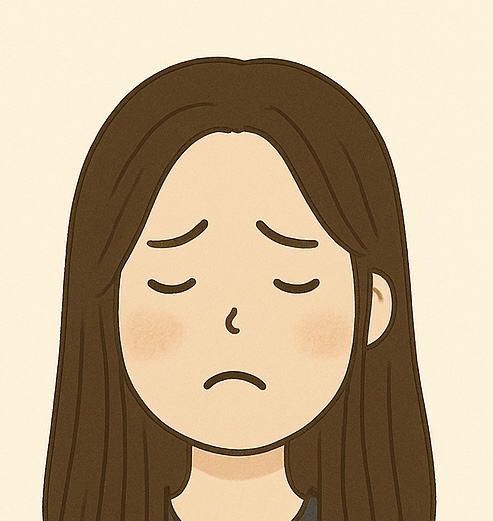
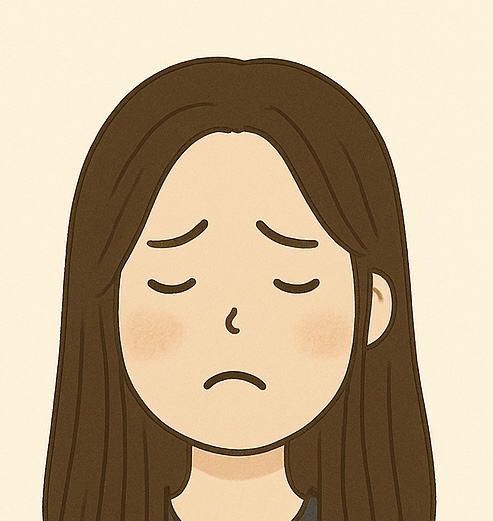
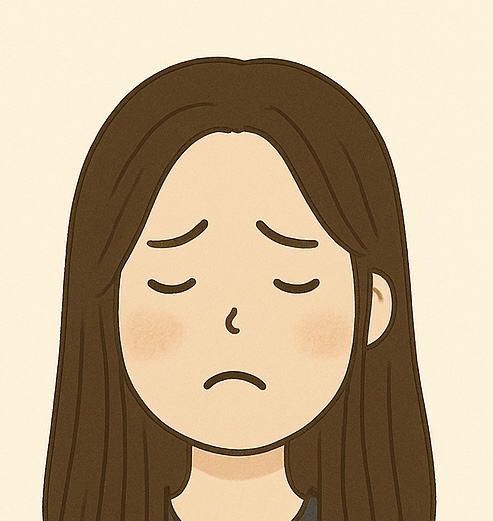
それぞれの良さもわかったけど結局自分の家庭にはどっちが合うのか?まだ決めきれないな。
そんな人は以下の実務フローで決めてみてください。
- 自宅の“冷凍庫の目安収納数”を測る(前述の計算でチェック)
- 週あたりの宅食利用予定数を決める(例:週3食〜週10食)
- 在宅率(受け取りのしやすさ)を確認 → 在宅が少ないなら冷凍一択
- 家族での“温めが頼めるか”を確認 → 誰も頼めない場合は冷蔵か加熱が簡単な冷凍を選ぶ
- まずはお試し(少量)を注文し、1か月運用してから本契約に移行
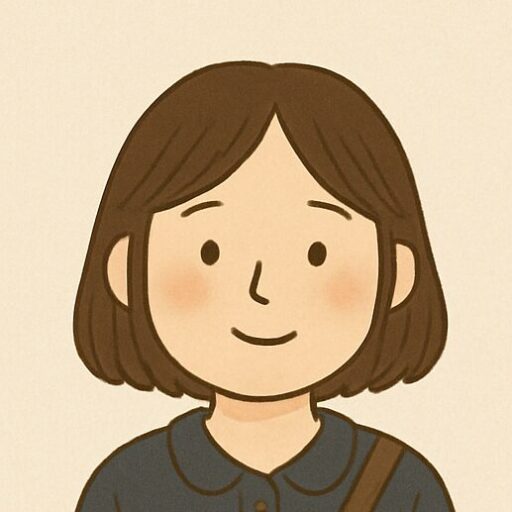
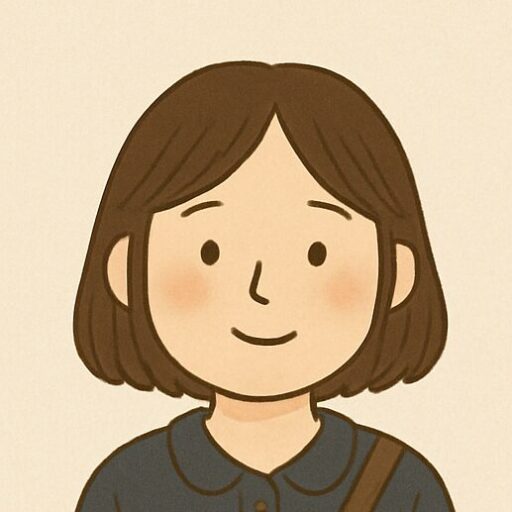
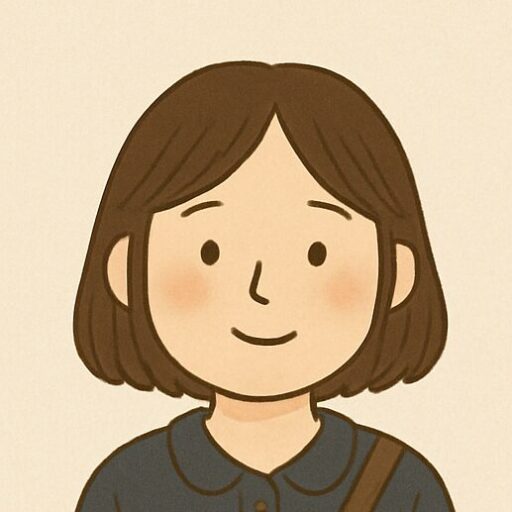
この6つの流れで考えれば大きな失敗はしないと思うよ。
それでもまだ決めきれない人の6つの最終チェックリスト
ここまで読んでいただいたことで冷凍or冷蔵宅食サービスを決められたのではないでしょうか?
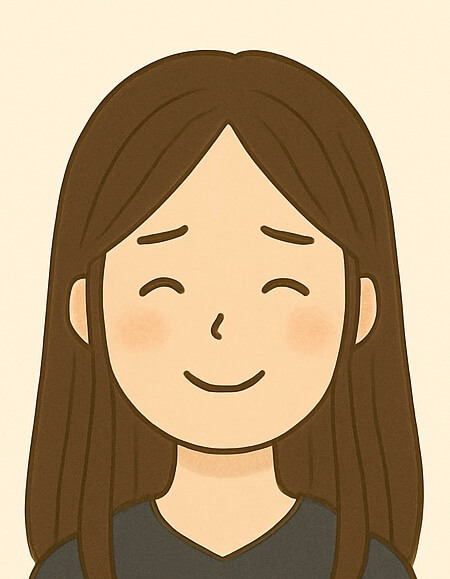
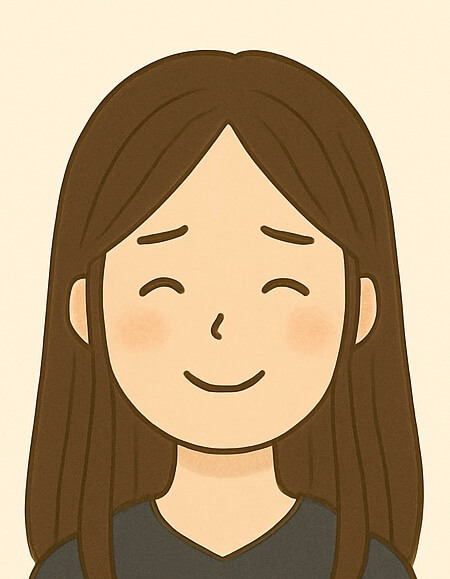
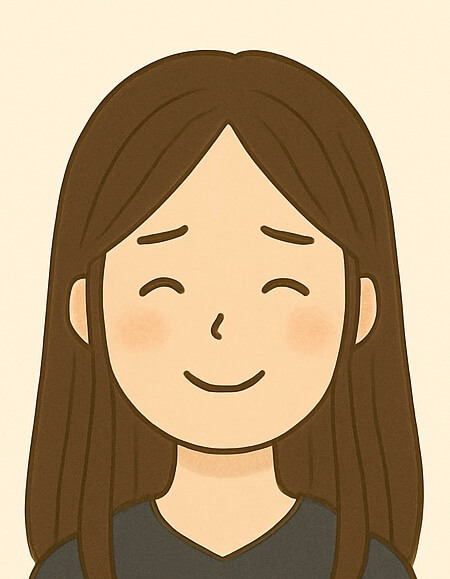
決めたつもりだけど抜けた観点あったかな?大丈夫かな?
と不安になっている人は以下の6つのチェックリストを確認してみてください。
- 冷凍庫に何食入るか測った?
- 受け取り回数と配送料の合計金額を試算した?(1食価格だけで判断しない)
- 加熱方法(電子レンジor湯煎)を家族が扱える?
- 揚げ物やサクサク系をどの程度気にするか整理した?
- 賞味期限(冷蔵は短い)を忘れずに確認した?
- 初回割引・クーポンは使える?(まずはお試しを!)
ここまで念入りに考えたのであれば、ほぼ失敗はありません。
まとめ:自分の暮らしに合わせた冷凍/冷蔵宅食で便利で美味しいを味わおう


冷凍宅食・冷蔵宅食はどちらが“使いやすいか”は 自分の生活リズム・設備・受け取りの自由度 によって決まります。
帰宅が遅くても夕飯を確実に用意したいなら、冷凍タイプを中心に利用することがおすすめです。
一方で冷凍庫が小さい/その日のうちに食べきりたいなら冷蔵タイプを検討するのが良いです。
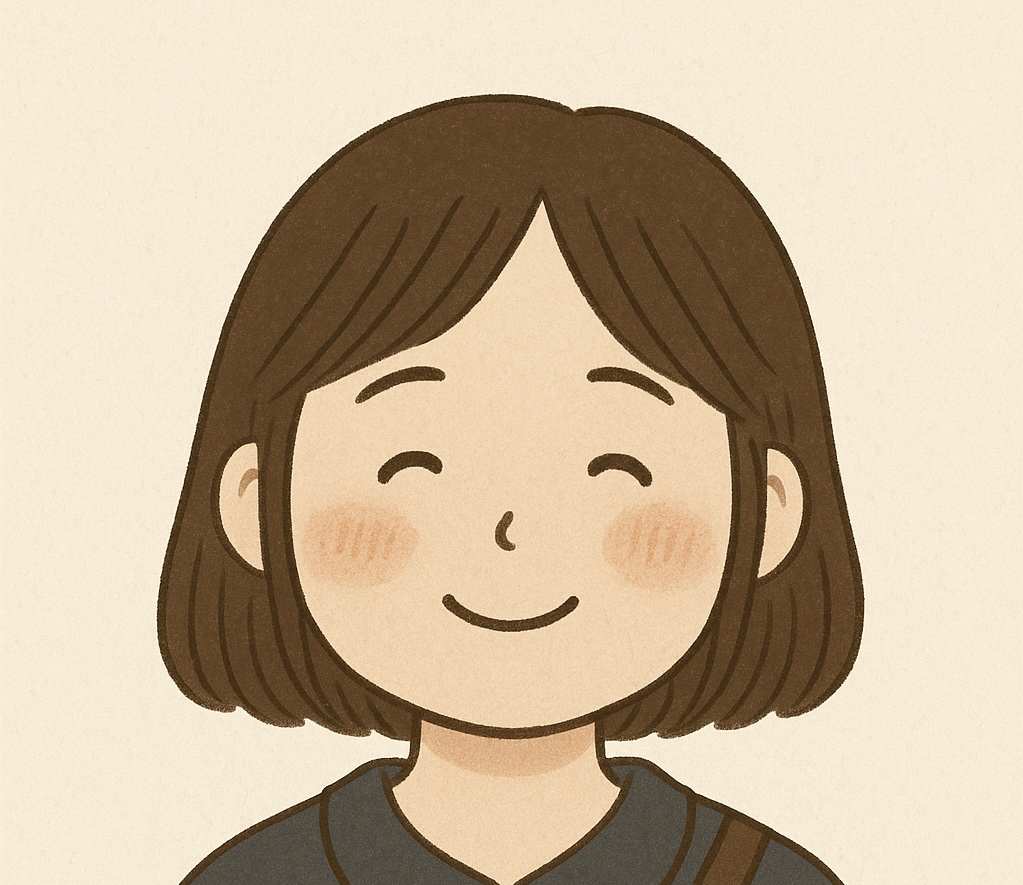
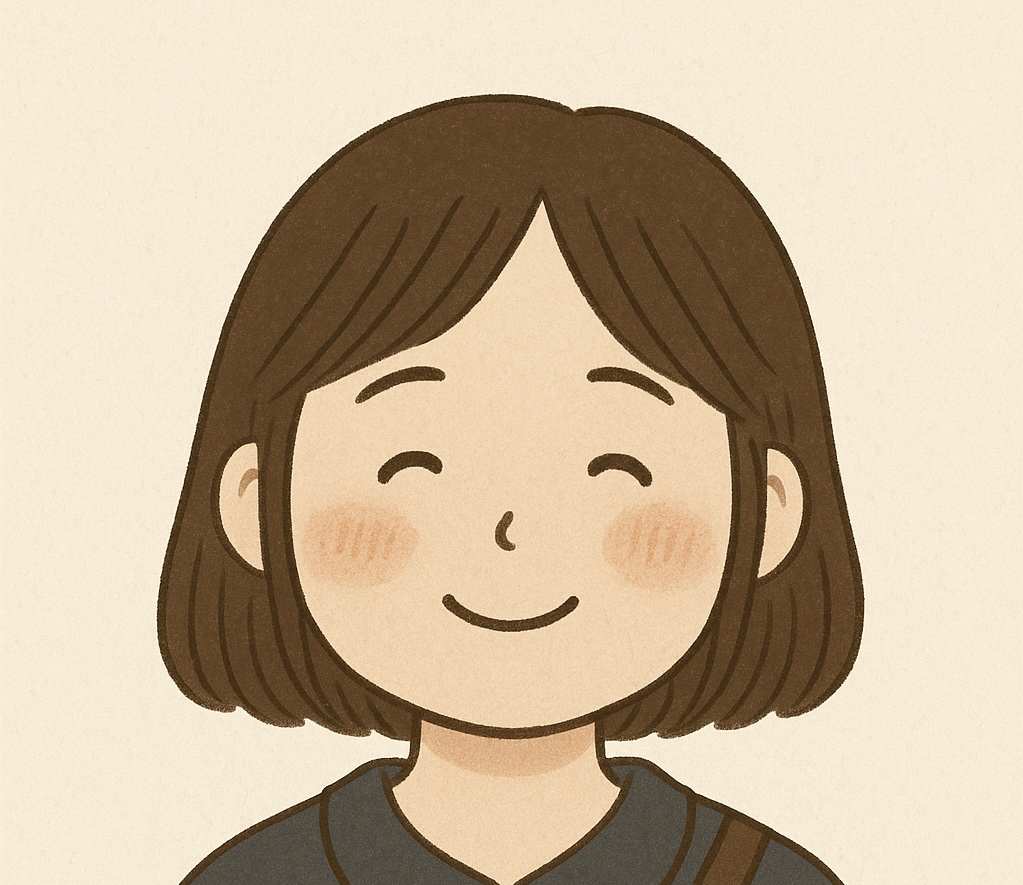
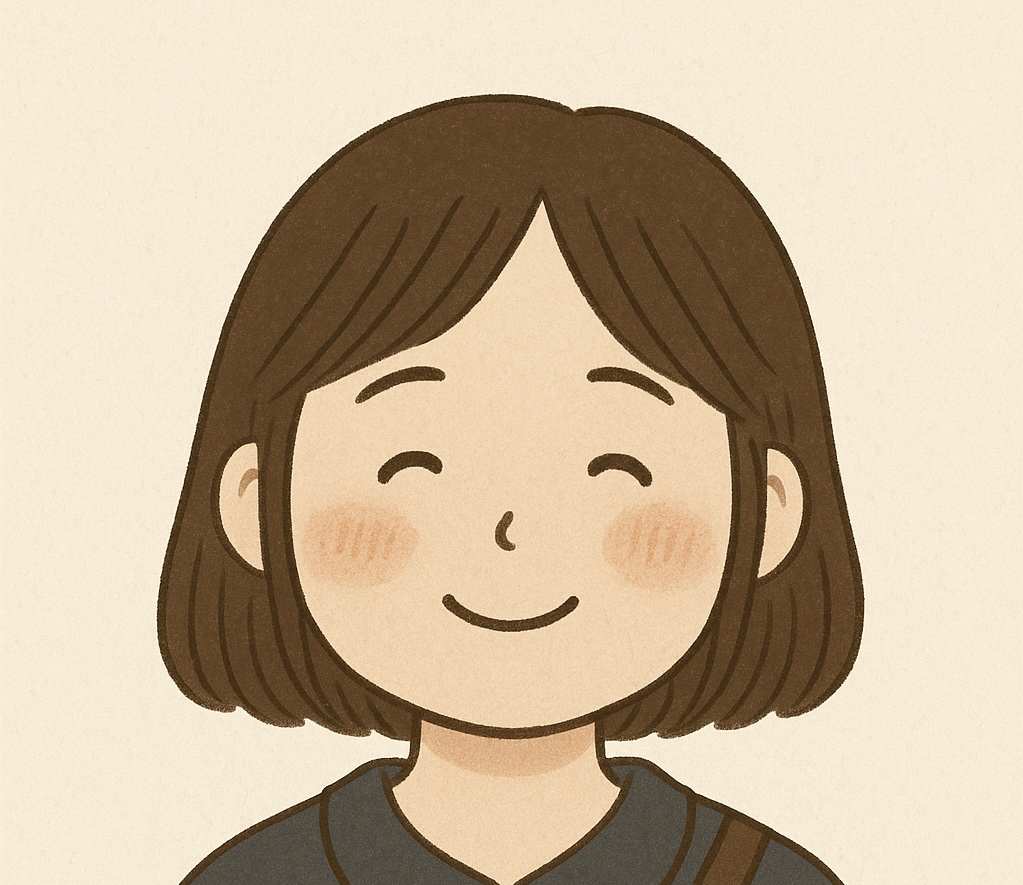
決めきれないのであれば両タイプとも試してみるのも良いかもしれません。
冷凍でまとめストック+冷蔵でその日の分、というハイブリッド型にしてみるのも良い方法です。
一度「少量のお試し」で冷凍・冷蔵両方を使ってみて、最終的に「自分がストレスなく使い続けられる方」を選ぶのが正解です。
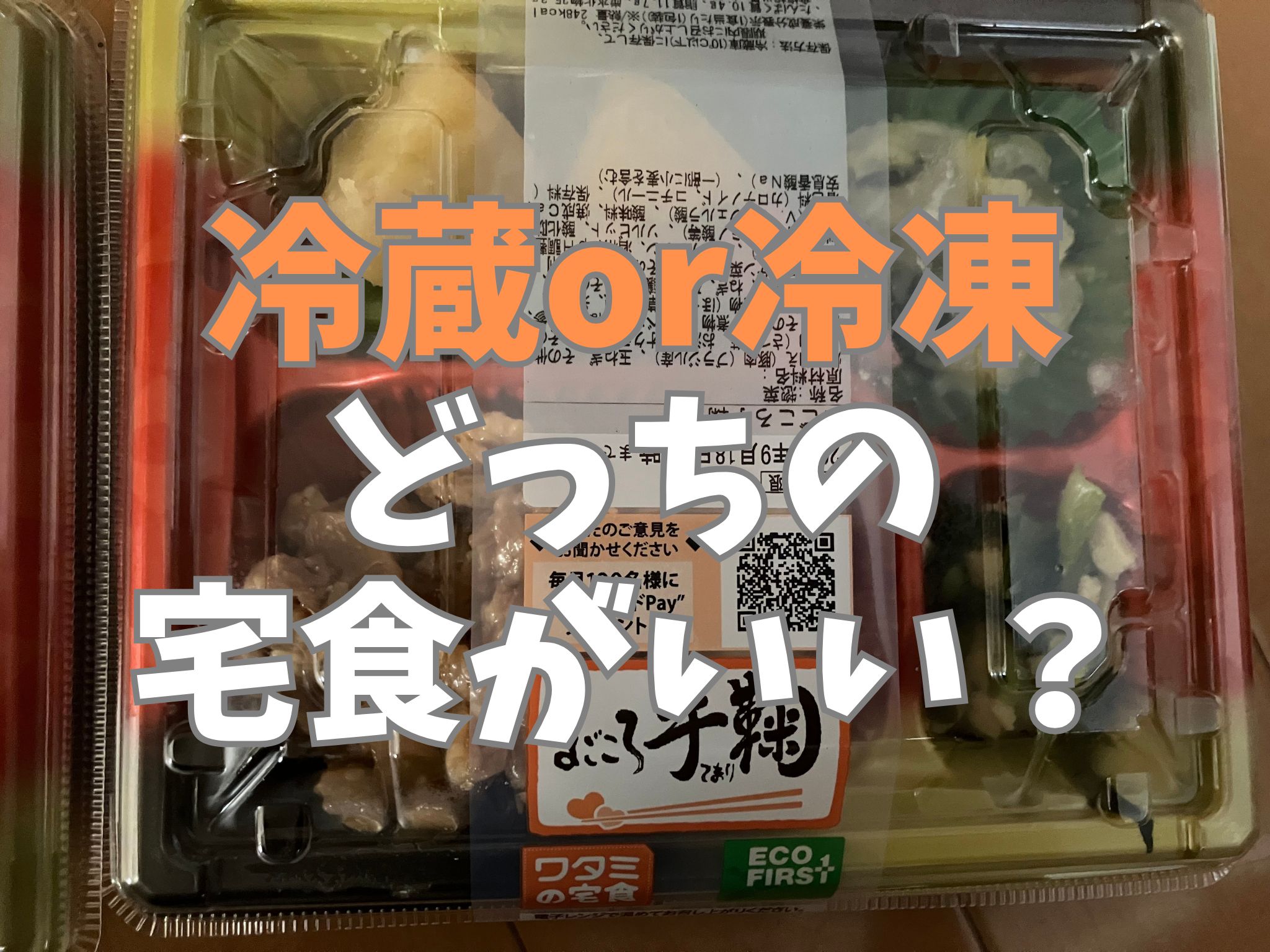
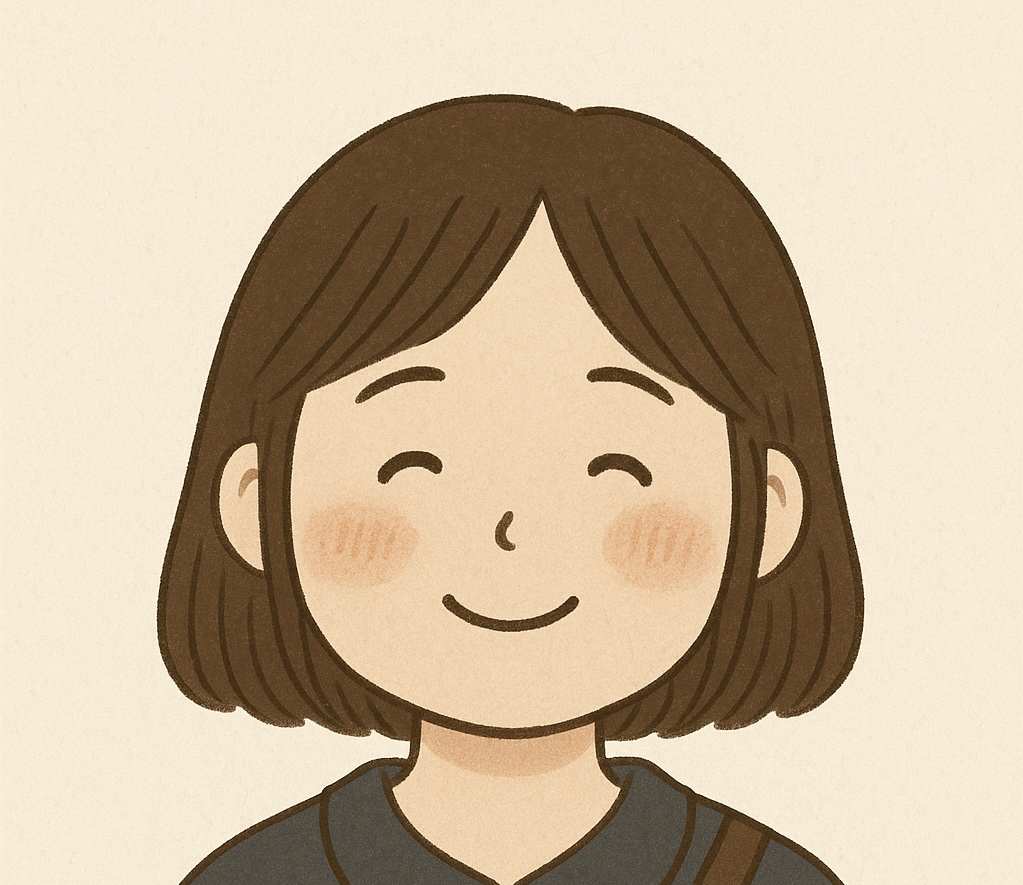
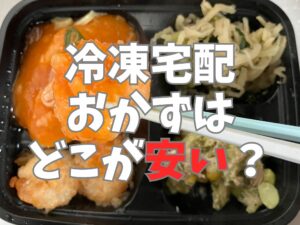






コメント