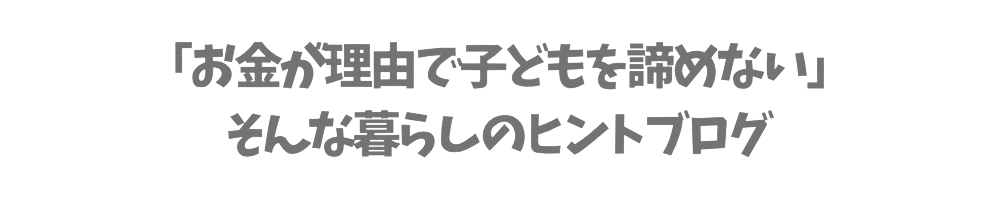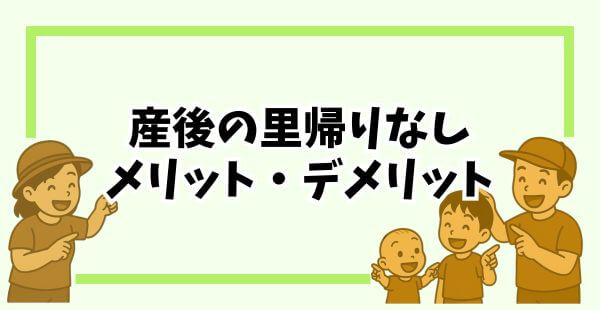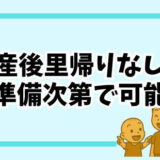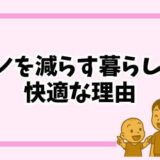この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
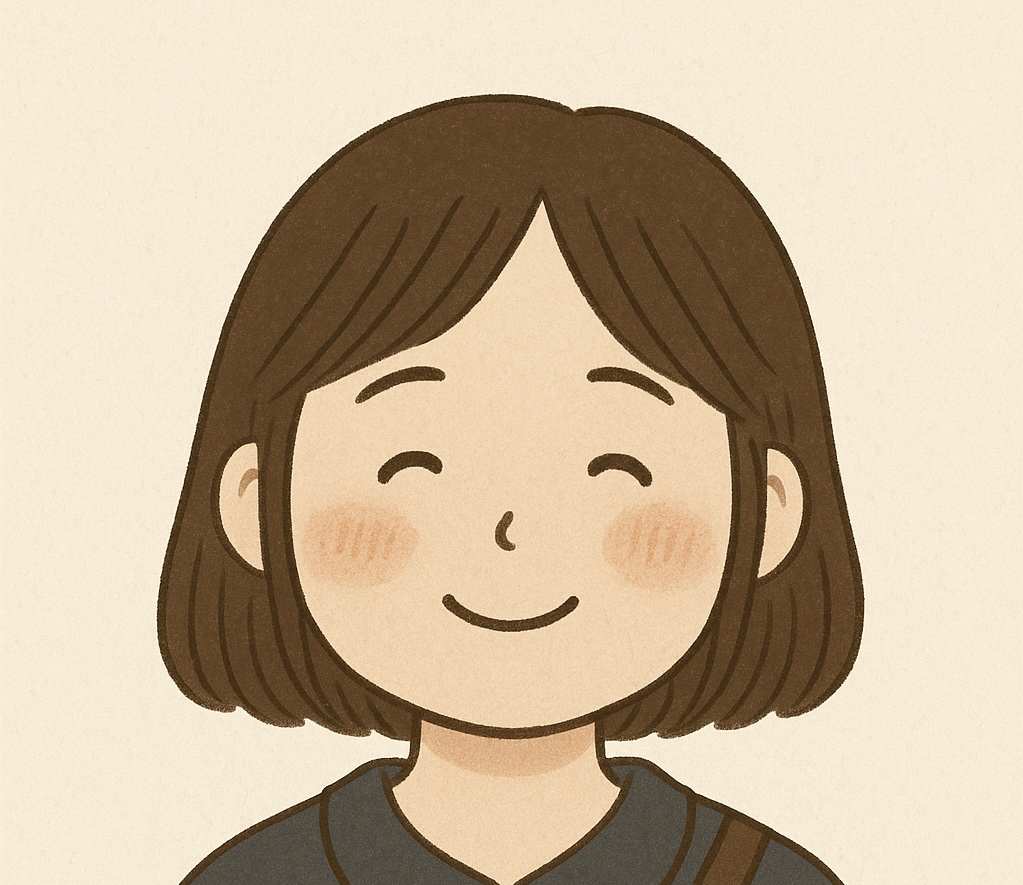
てせんママです。
育休中・夫1馬力で月5万円貯金成功!
「お金が理由で子どもを諦める人を減らしたい」という思いで、小さく暮らす工夫や子どもとの日々を発信しています。
産後の里帰りをしないつもりだけど、実際ちゃんと育児できるかな?
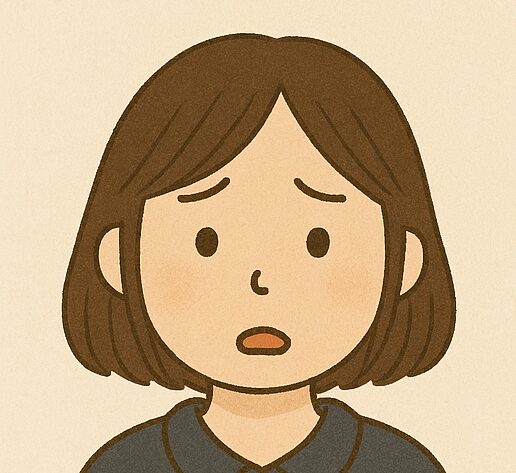
私も産後の里帰りをしなかったので同じ不安を抱えていました。
産後に里帰りするのが当たり前と言われることも多いですが、私はあえて実家に帰らず
夫と赤ちゃんの3人で新生児育児をスタートしました。
✔︎ サポートなしで大丈夫?
✔︎ 実家に戻らないなんて無謀?
と不安になりますよね。
でも実際にやってみたからこそ感じた “良かったこと” も “しんどかったこと” もたくさんありました。
今回は里帰りしなかった理由とメリット・デメリット。快適に乗り切るコツをリアルな体験談ベースでまとめます。

「自分は里帰りする?しない?」と悩む人が、“自分たちに合った産後スタイル” を安心して選べるようになります。
- 私が里帰りしなかった理由
- 里帰りしない育児のメリット・デメリット
- 乗り切るために実践した具体的な工夫
- 里帰りしない育児が向いているのはこんな人
里帰りをしない産後育児は決して“無謀”ではありません。
実際に我が家では、夫婦で役割分担をして協力することで乗り切ることができました。
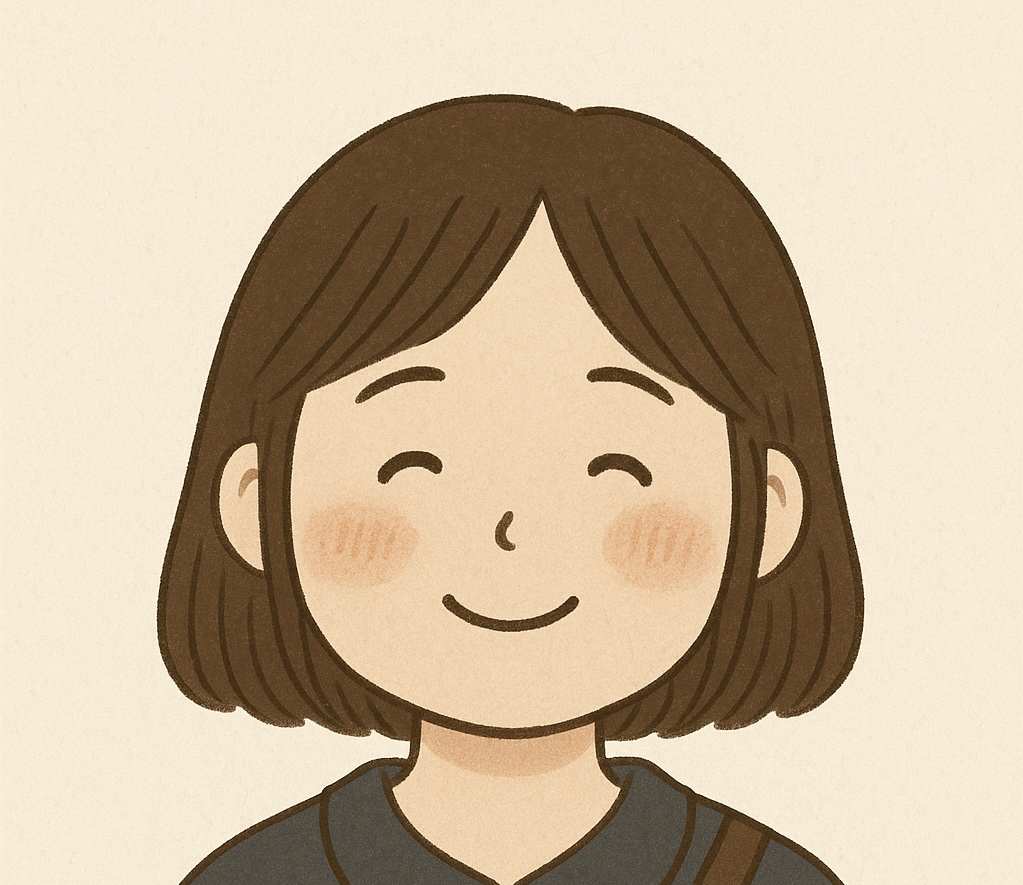
夫婦ふたりで新生児期に挑んだことで、早い段階から「家族」としての自覚が芽生え、絆が深まったように感じています。
産後ママにとって一番のサポーターは今後一緒に育児をしていく“夫”です。
もちろん、体力的にも精神的にも大変な産後です。
でも、便利な宅配サービスや家電。そして「ふたりで乗り越える」という覚悟さえあれば、里帰りをしなくても乗り越えられます。
我が家では妊娠中から
「出産後にどこでどんなふうに過ごすか?」
を何度も話し合い、あえて里帰りをしないことを選択しました。
その決断には、大きく2つの理由があります。
産後すぐの新生児期は、一日のほとんどを授乳・オムツ替え・寝かしつけで過ごすハードな時期です。
この時期を実家で過ごしてしまうと、どうしてもパパがサポートできる機会が少なくなってしまいます。
そこで我が家では、最初から自宅で夫婦ふたりで乗り越えることを選びました。
結果、夫はオムツ替えやミルク作り、寝かしつけまで“最初からできる人”になりました。
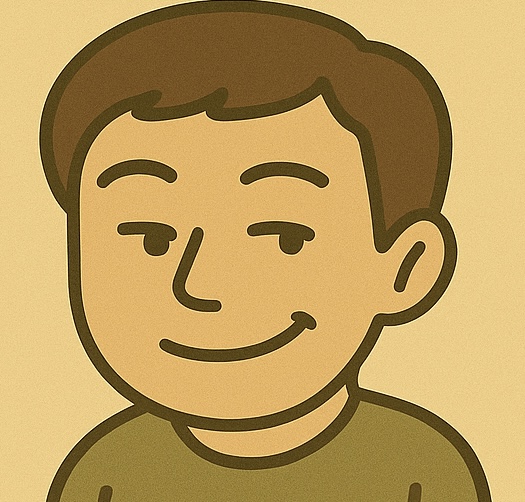
沐浴時期から今現在も子どもとのお風呂は僕が担当しているよ。
育児スキルと父親としての自覚が早い段階で芽生えました。
これはその後の育児においても、非常に大きなメリットでした。
私は両親と良好な関係を保っていますが、社会人になってからは一人暮らしを始めて実家に“寝泊まりする”ことは全くなくなりました。
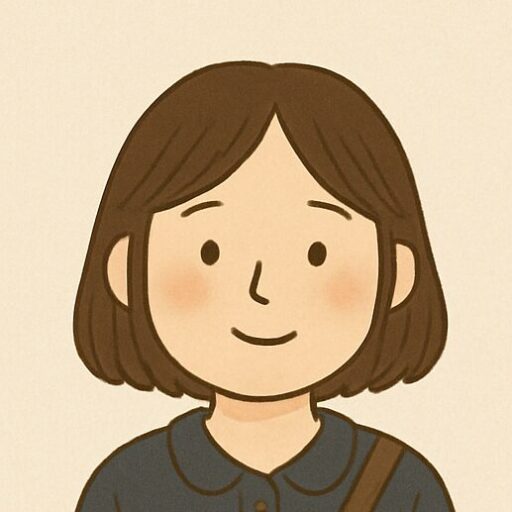
大人になってからの実家は、どこか気楽なようでいて、気を遣ってしまう場所でした。
今でも子どもを連れて遊びに行きますが、あくまで“日帰りでちょっと立ち寄る場所”というスタンスです。
私にとって実家は、
✔︎ 何かしてもらうたびに申し訳なくなる
✔︎ 自分のペースで生活できない
そんなストレスが知らず知らずのうちに溜まってしまう場所でもありました。
それなら、多少大変でも“自分の家”で赤ちゃんとの生活をスタートした方が、私には合っていると思いました。
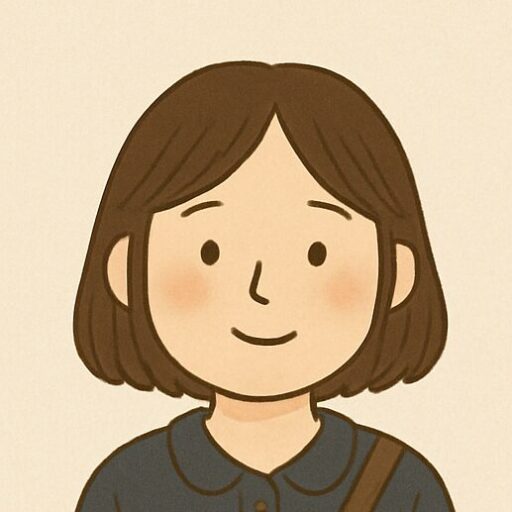
自宅であれば気兼ねなく過ごせますし、宅配食や便利家電といったサービスもフル活用できます。
✔︎ 完璧を目指しすぎない
✔︎ 夫婦で協力する
というスタンスで乗り切った結果、精神的にもゆとりが生まれ、里帰りをしなかったことは我が家にとって正解だったと感じています。

産後すぐに
「ふたりでこの子を育てていこう」
という意識が強くなり、自然と協力体制が生まれました。
お互いに試行錯誤しながら乗り越えたことで、“チームとしての絆”が一気に深まりました。
事前に「産後はホルモンの影響で情緒が不安定になるかもしれない」と伝えていたおかげで
夫も心構えができており、思った以上に衝突することなく穏やかに過ごすことができました。
里帰りをしなかったことで、パパも新生児期から育児の当事者になります。
✔︎ オムツ替え
✔︎ ミルク作り
✔︎ 寝かしつけ
✔︎ 家事のサポート
夫が“最初から戦力”になってくれたおかげで、その後の生活でも分担が当たり前になりました。
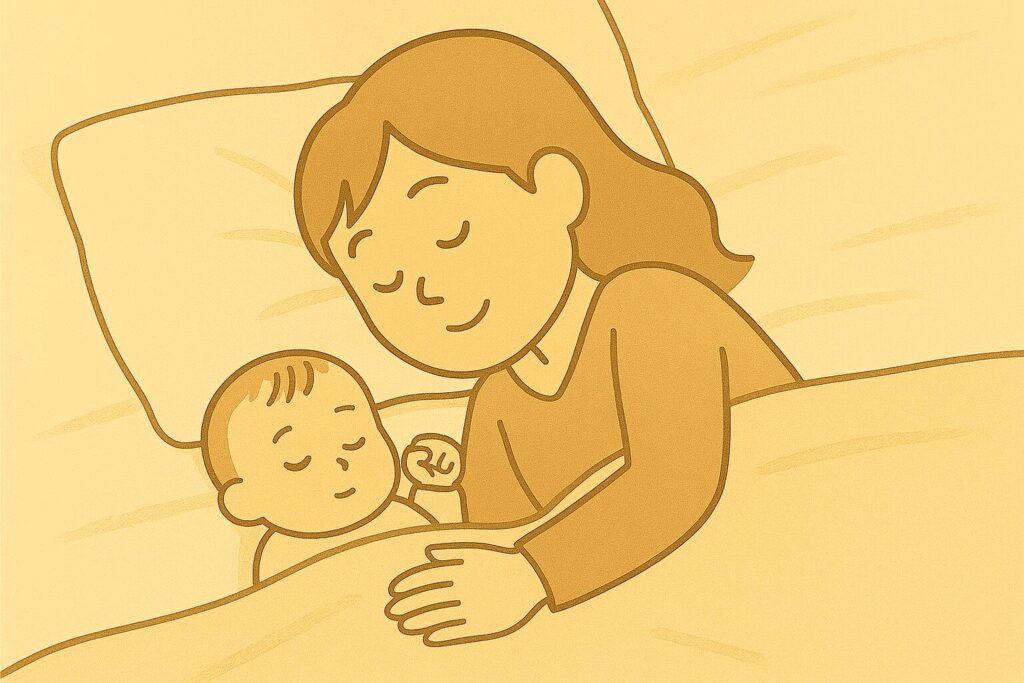
実家だと
✔︎ やってもらって申し訳ない
✔︎ ペースが掴みにくい
という気疲れがありそうでしたが、自宅なら完全に自分たちのルールなので
✔︎ 好きなときに休み
✔︎ 気楽な格好でゴロゴロ
✔︎ 宅配食や家電も活用
と、ストレスゼロで過ごせたのは大きな魅力でした。
夜中の授乳や泣き声も「誰かに気を遣う必要がない」ことで、精神的にとてもラクに感じました。
赤ちゃんや夫婦のペースに合わせて少しずつ生活リズムを作ることができました。
結果としてスムーズに“産後の暮らしモード”へ移行できたと思います。

出産後は、悪露・寝不足・会陰の痛み・ホルモンバランスの乱れなどで、想像以上に身体がしんどい状態になります。
ですが、里帰りしない場合は身近に頼れる大人が夫しかいません。
「手伝ってほしいけど、夫は仕事でいない」という時間帯も多く
日中はひとりで授乳・オムツ替え・抱っこを耐えるしかない状況になります。
実家なら交代で寝られる場面も、自宅だと「自分がやるしかない」が連続です。
体力気力の回復が遅れがちになるのは覚悟しておく必要があります。
赤ちゃんのお世話だけでも精一杯なのに、家事も通常営業で降りかかってくるのが自宅育児です。
我が家は、ミールキット・宅配弁当・食洗機・ドラム式洗濯乾燥機など
“お金で時間を買う”方法を総動員しました。
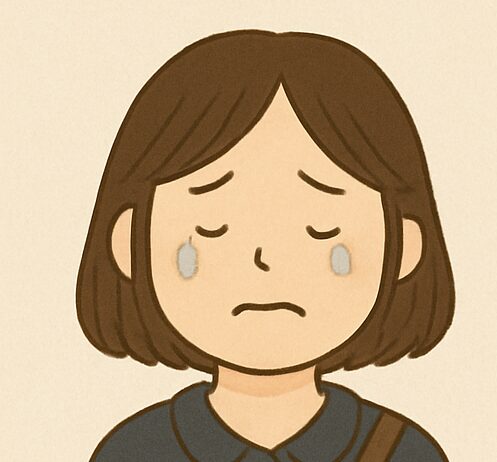
これらがなければ回らなかったと言っても過言ではありません。
「里帰りしない=家事もやる」ではなく、“家事はお金に頼る前提”で考えた方が、結果的にラクになります。

夫が仕事に出ている間は実質“ワンオペ”になります。
泣き続ける赤ちゃんを抱っこしながら「いつまで続くの?」と涙がにじむ日もありました。
✔︎ 誰とも話さない1日 → 孤独でメンタルが沈む
✔︎ 赤ちゃんが泣き止まない → 自分を責めてしまう
✔︎ 疲れているのに寝られない → 情緒が不安定になる
この“閉ざされた時間”こそが、里帰りしないデメリットの最大ポイントです。
ママのメンタル維持のためにも
✔︎ 夫婦のこまめな声掛け
✔︎ 時短家電
✔︎ たまのデリバリー
など、“完璧を目指さない暮らし”が大事です。

- 夫が協力的 or 在宅時間が多い
- 家電や宅配で時短できる環境がある
- 実家に気を遣ってしまうタイプ
こんな人には「里帰りしない育児」は向いています。
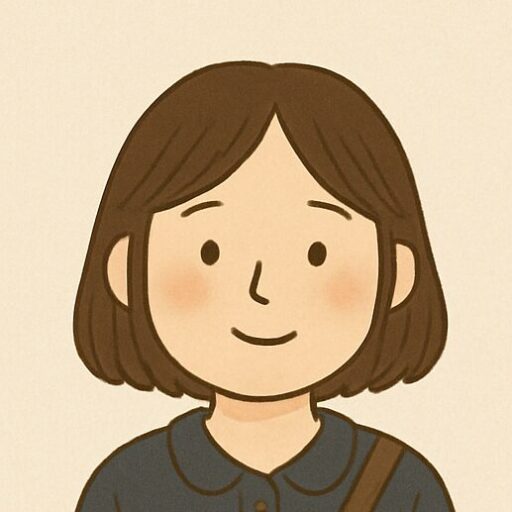
ワンオペ要素が強い・夫の帰宅が遅いご家庭は、無理せず里帰りを選んだ方が安心かもしれません。
子どもとお母さんが元気に暮らすためにどちらが良いのかで決めることがベストです。
里帰りしなくても、工夫と夫婦の協力があれば産後は乗り切れます。
大事なのは「何が正解か」より、“自分たちに合った選択をすること”です。
もし「里帰りしないのってアリかな?」と迷っているなら、我が家の体験が少しでも後押しになれば嬉しいです。
↓この記事を書いた人↓

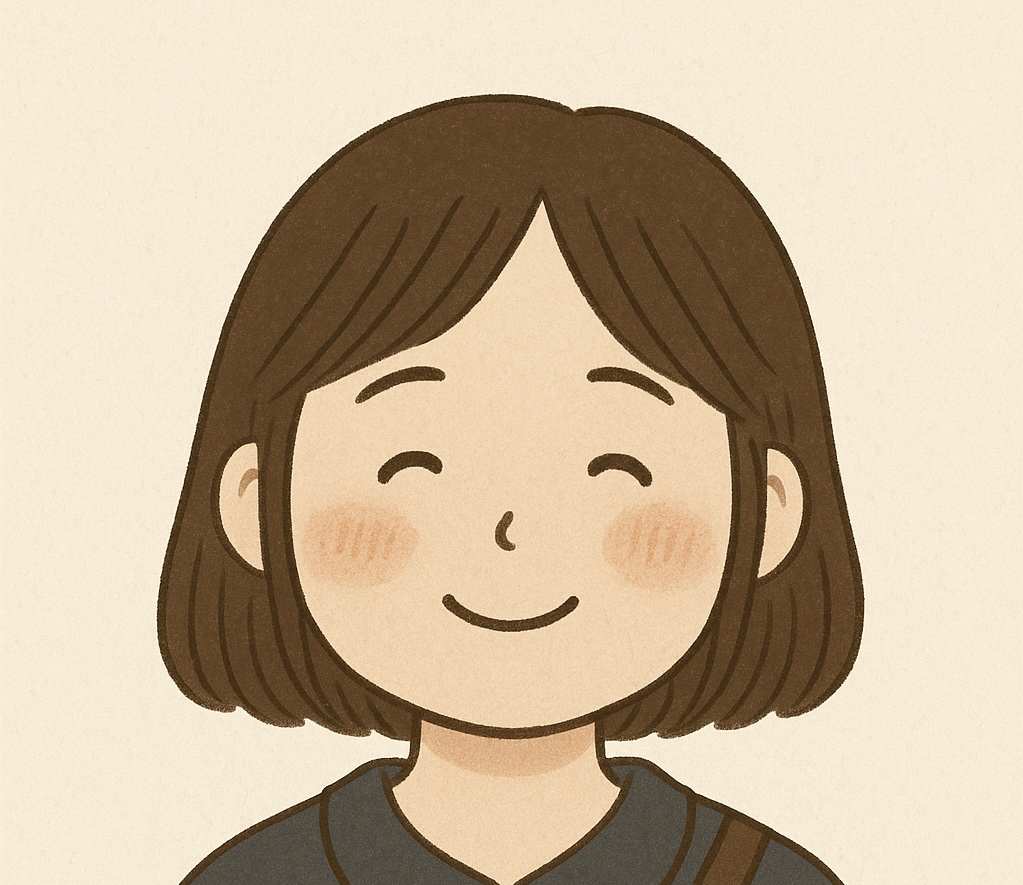
てせんママ
夫と息子・娘の4人家族。田舎暮らし。住宅ローンあり&車2台持ちでも毎月5万円以上の貯金成功。
\小さな暮らしで、節約×自己投資で“経済的理由で子どもを諦めない暮らし”/をブログで発信中
▶︎ 誰でも、月3万円の貯金ができる生活になる暮らし方・考え方。
▶︎ Instagramもやってます → @tesen_mama.blog